ブログ

ブログ
もう悩まない!肩こりの原因となる寝方とは?鍼灸の効果と改善ストレッチで朝スッキリ!
2025/08/04
毎朝、肩こりのせいでスッキリ起きられない…そんなお悩みを抱えていませんか? 実は、その肩こりの原因は、寝方にあるかもしれません。
このページでは、肩こりと寝方の深~い関係について詳しく解説します。高すぎる枕、低すぎる枕、うつ伏せ寝など、肩こりを悪化させる寝方の具体的な例から、寝方以外の原因、そして効果的な改善策まで網羅的にご紹介。さらに、肩こりのつらい症状を緩和する鍼灸の効果やメカニズムについても分かりやすく説明します。
肩甲骨はがしや首回しなど、すぐに実践できるストレッチもご紹介するので、ぜひ今日から試してみてください。朝起きた時の肩の軽さを実感し、快適な一日をスタートさせましょう!
1. 肩こりと寝方の関係
毎晩の睡眠は、日中の疲れを癒すための大切な時間です。しかし、間違った寝方が肩こりを招き、せっかくの休息が台無しになってしまうことも。実は、肩こりと寝方には深い関係があるのです。毎朝肩こりで悩んでいる方は、自分の寝方を見直してみましょう。
1.1 間違った寝方が肩こりを招く!?
肩こりの原因の一つに、寝方があります。睡眠中は長時間同じ姿勢を続けるため、身体への負担が大きくなりやすいのです。特に、以下のような寝方は肩こりを悪化させる可能性があります。
1.1.1 高すぎる枕、低すぎる枕
枕の高さが合っていないと、首や肩の筋肉に負担がかかり、肩こりの原因になります。高すぎる枕は首を過度に曲げ、低すぎる枕は首を反らせるため、どちらも肩や首の筋肉に負担がかかります。自分に合った高さの枕を選ぶことが重要です。
| 枕の高さ | 影響 |
| 高すぎる | 首が過度に曲がり、肩や首の筋肉に負担がかかる。呼吸が浅くなることも。 |
| 低すぎる | 首が反り、肩や首の筋肉が緊張する。いびきの原因になることも。 |
1.1.2 うつ伏せ寝
うつ伏せ寝は、首を長時間横に向けた状態になるため、首や肩の筋肉に負担がかかり、肩こりを悪化させる原因となります。また、呼吸が浅くなったり、腰に負担がかかったりするなど、他の身体への悪影響も懸念されます。どうしてもうつ伏せで寝たい場合は、なるべく短い時間にする、薄い枕を使うなどの工夫をしましょう。
1.1.3 同じ側ばかりで寝る
同じ側ばかりで寝ていると、片側の肩や首に負担が集中し、肩こりの原因になります。左右均等に体重がかかるように、寝る姿勢を意識的に変える、抱き枕を使うなどして、身体のバランスを保つように心がけましょう。寝返りをスムーズに打てるようなマットレスを選ぶことも大切です。
2. 肩こりの原因
肩こりは、寝方以外にも様々な原因が考えられます。日常生活の習慣や環境、身体的な要因など、多岐にわたる原因を理解することで、効果的な対策を立てることができます。
2.1 寝方以外の原因
2.1.1 デスクワーク
長時間のパソコン作業やデスクワークは、肩こりの大きな原因の一つです。同じ姿勢を長時間続けることで、肩や首周りの筋肉が緊張し、血行不良を引き起こします。特に、画面を見続けることで頭が前に出てしまい、猫背になりやすい姿勢は、肩への負担をさらに増大させます。
2.1.2 運動不足
運動不足も肩こりの原因となります。運動不足になると、筋肉が衰え、血行が悪くなります。筋肉が衰えると、姿勢を維持する力が弱まり、猫背になりやすくなります。猫背は肩甲骨の動きを制限し、肩や首周りの筋肉に負担をかけ、肩こりを引き起こします。また、血行不良も筋肉の緊張を招き、肩こりを悪化させます。
2.1.3 冷え性
冷え性は、血行不良を招き、筋肉が緊張しやすくなるため、肩こりの原因となります。特に、女性は男性に比べて筋肉量が少ないため、冷えを感じやすく、肩こりになりやすい傾向があります。 冷えから身体を守るために、無意識に肩をすくめる姿勢をとることも、肩こりの原因となります。
2.1.4 ストレス
ストレスは、自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高めるため、肩こりの原因となります。ストレスを感じると、交感神経が優位になり、血管が収縮して血行が悪くなります。また、筋肉も緊張しやすくなり、肩こりだけでなく、頭痛や吐き気などの症状が現れることもあります。
2.1.5 猫背
猫背は、肩甲骨の位置がずれることで、肩や首周りの筋肉に負担がかかり、肩こりの原因となります。猫背の姿勢では、頭が前に出て、肩が内側に巻き込まれた状態になります。この姿勢は、肩甲骨を正しい位置に保つ筋肉に負担をかけ、肩こりだけでなく、呼吸が浅くなったり、内臓の機能が低下するなどの悪影響も及ぼします。
| 原因 | 詳細 | 対策 |
| デスクワーク | 長時間同じ姿勢での作業により、肩や首の筋肉が緊張し血行不良に。 | こまめな休憩、ストレッチ、正しい姿勢の維持 |
| 運動不足 | 筋肉の衰え、血行不良、姿勢が悪くなることで肩こり発生。 | 適度な運動、ウォーキング、筋トレ |
| 冷え性 | 血行不良により筋肉が緊張。肩をすくめる姿勢も原因に。 | 体を温める、温かい飲み物、適切な衣服の着用 |
| ストレス | 自律神経の乱れ、筋肉の緊張、血行不良を引き起こす。 | ストレス解消法の実践、リラックス、十分な睡眠 |
| 猫背 | 肩甲骨の位置のずれ、肩や首への負担増加。 | 姿勢改善、ストレッチ、猫背矯正グッズの使用 |
3. 鍼灸で肩こり改善
肩こりは、現代社会において多くの人が抱える悩みのひとつです。デスクワークやスマートフォンの長時間使用など、日常生活の様々な要因が肩こりの原因となります。肩こりに悩まされている方の多くは、マッサージやストレッチなどのセルフケアを試みることも多いでしょう。しかし、根本的な原因にアプローチしなければ、なかなか改善しないのも事実です。そこで、注目されているのが鍼灸治療です。古くから伝わる東洋医学に基づいた鍼灸治療は、肩こりの根本的な改善に効果的であると考えられています。
3.1 鍼灸が肩こりに効くメカニズム
鍼灸治療は、肩こりの改善に様々な効果をもたらします。そのメカニズムを詳しく見ていきましょう。
3.1.1 血行促進効果
肩こりの原因のひとつに、血行不良が挙げられます。長時間のデスクワークや猫背などの姿勢不良は、肩や首周りの筋肉を緊張させ、血流を滞らせてしまいます。鍼灸治療では、ツボに鍼を刺すことで、筋肉の緊張を緩和し、血行を促進します。血流が改善されると、筋肉や組織への酸素供給が向上し、老廃物の排出もスムーズになります。その結果、肩こりの緩和につながるのです。
3.1.2 筋肉の緊張緩和
肩こりは、筋肉の過剰な緊張によって引き起こされます。鍼灸治療は、筋肉の緊張を緩和する効果があります。鍼刺激は、筋肉の深部まで到達し、硬くなった筋肉を柔らかくほぐします。また、鍼灸治療は、脳内にエンドルフィンなどの鎮痛作用のある物質を分泌させ、痛みを軽減する効果も期待できます。筋肉の緊張が和らぐことで、肩の可動域が広がり、こり固まった状態から解放されます。
3.1.3 自律神経の調整
自律神経の乱れも、肩こりの原因のひとつです。ストレスや不規則な生活習慣は、自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高めます。鍼灸治療は、自律神経の調整にも効果的です。ツボへの刺激は、自律神経のバランスを整え、リラックス効果をもたらします。自律神経が安定することで、筋肉の緊張が緩和され、肩こりの改善につながります。
鍼灸治療が肩こりに効果的なメカニズムをまとめると、以下のようになります。
| 効果 | メカニズム |
| 血行促進 | 筋肉の緊張緩和により血流が改善され、酸素供給と老廃物排出が促進される |
| 筋肉の緊張緩和 | 鍼刺激が筋肉の深部に到達し、硬くなった筋肉を柔らかくほぐす。また、エンドルフィンなどの鎮痛物質の分泌を促進する |
| 自律神経の調整 | ツボへの刺激が自律神経のバランスを整え、リラックス効果をもたらす |
鍼灸治療は、これらのメカニズムを通して肩こりの根本的な改善を目指します。肩こりに悩んでいる方は、鍼灸治療を試してみる価値があるでしょう。専門家による適切な施術を受けることで、より効果的な改善が期待できます。
4. 肩こり改善ストレッチ
肩こりは、日々の生活習慣の中で知らず知らずのうちに蓄積してしまう厄介なものです。肩こりの原因である筋肉の緊張や血行不良を改善するためには、ストレッチが効果的です。ここでは、寝る前と朝に行うと効果的なストレッチをご紹介します。
4.1 寝る前におすすめのストレッチ
寝る前のストレッチは、一日の疲れを癒し、リラックスした状態で眠りにつくために重要です。肩や首周りの筋肉を優しくほぐすことで、質の高い睡眠を得られるようになり、肩こりの改善にも繋がります。
4.1.1 肩甲骨はがし
肩甲骨を動かすことで、肩周りの筋肉の柔軟性を高め、血行を促進します。肩甲骨を意識的に動かすことで、肩こりの原因となる筋肉の緊張を和らげることができます。
- 両腕を前に伸ばし、手のひらを合わせます。
- 息を吸いながら、両腕を頭の上まで持ち上げます。
- 息を吐きながら、両肘を曲げ、肩甲骨を寄せるように意識しながら、両腕を後ろに引きます。
- この動作を5~10回繰り返します。
4.1.2 首回しストレッチ
首の筋肉は、デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けることで凝り固まりやすく、肩こりの原因となります。首をゆっくりと回すことで、首周りの筋肉をほぐし、血行を促進します。
- 頭をゆっくりと右に倒し、5秒間キープします。
- 次に、頭をゆっくりと後ろに倒し、5秒間キープします。
- 同様に、頭を左に倒し、5秒間キープします。
- 最後に、頭をゆっくりと前に倒し、5秒間キープします。
- この動作を3~5回繰り返します。
4.2 朝におすすめのストレッチ
朝のストレッチは、寝ている間に固まった体をほぐし、一日を快適にスタートするために効果的です。肩周りの筋肉を動かすことで、血行が促進され、肩こりの予防や改善に繋がります。
4.2.1 腕回しストレッチ
腕を大きく回すことで、肩関節周りの筋肉をほぐし、可動域を広げます。肩甲骨から動かすことを意識することで、より効果的に肩こりの改善に繋がります。
- 両足を肩幅に開き、両腕を肩の高さまで上げます。
- 腕を大きく後ろ回しで10回まわします。
- 次に、腕を大きく前回しで10回まわします。
4.2.2 肩甲骨寄せストレッチ
肩甲骨を寄せることで、肩甲骨周りの筋肉を強化し、姿勢の改善にも効果があります。胸を張ることを意識することで、より効果的に肩甲骨を寄せられます。
- 両足を肩幅に開き、両腕を体の横に下ろします。
- 息を吸いながら、両肩甲骨を中央に寄せるように意識し、胸を張ります。
- 息を吐きながら、元の姿勢に戻ります。
- この動作を10~15回繰り返します。
これらのストレッチは、肩こりの改善だけでなく、姿勢改善、血行促進、リラックス効果など、様々な効果が期待できます。毎日継続して行うことで、より効果を実感できるでしょう。ご自身の体調に合わせて、無理のない範囲で行ってください。
4.3 ストレッチの効果を高めるポイント
ストレッチの効果を最大限に引き出すためには、いくつかのポイントに注意することが大切です。以下のポイントを意識しながらストレッチを行いましょう。
| ポイント | 詳細 |
| 呼吸を意識する | ストレッチを行う際は、深い呼吸を意識しましょう。息を吸いながら筋肉を伸ばし、息を吐きながら筋肉を緩めることで、より効果的に筋肉をほぐすことができます。 |
| 反動をつけない | ストレッチは、ゆっくりとした動作で行うことが大切です。反動をつけると筋肉を痛める可能性がありますので、注意しましょう。 |
| 無理をしない | 痛みを感じる場合は、無理にストレッチを続けないでください。自分の体の状態に合わせて、適切な強度で行うことが大切です。 |
| 継続して行う | ストレッチの効果を実感するためには、継続して行うことが重要です。毎日数分でも良いので、習慣的にストレッチを行いましょう。 |
5. 肩こり解消グッズ
肩こりは、日々の生活習慣や環境によって引き起こされることが多いです。質の高い睡眠や正しい姿勢を意識することはもちろんですが、自分に合ったグッズを使うことで、肩こりの改善や予防に繋がることがあります。
5.1 枕
睡眠中の姿勢は、肩こりに大きく影響します。自分に合った枕を選ぶことは、肩こり解消への第一歩と言えるでしょう。
5.1.1 自分に合った高さの枕を選ぶ
高すぎる枕は首に負担をかけ、低すぎる枕は頭が不安定になり、どちらも肩こりの原因となります。仰向けで寝たときに、首が自然なS字カーブを保てる高さが理想です。体型や寝姿勢によって適切な高さは異なるため、実際に試してみるのがおすすめです。
5.1.2 素材にもこだわろう
枕の素材は、寝心地だけでなく、通気性や耐久性にも関わります。低反発素材、高反発素材、羽根、そば殻など、様々な素材があります。それぞれの素材の特徴を理解し、自分の好みに合ったものを選ぶことが大切です。たとえば、通気性を重視するのであれば、そば殻やパイプ素材がおすすめです。フィット感を重視するのであれば、低反発素材がおすすめです。
| 素材 | 特徴 | メリット | デメリット |
| 低反発 | 体圧分散性に優れている | 頭や首にフィットし、負担を軽減 | 通気性が悪い場合がある |
| 高反発 | 反発力があり、寝返りがしやすい | 体圧分散性も高く、通気性も良い | 柔らかすぎる枕が苦手な人には合わない場合も |
| 羽根 | 柔らかく、ふんわりとした感触 | 通気性が良く、蒸れにくい | 耐久性が低く、へたりやすい |
| そば殻 | 通気性抜群で、熱がこもりにくい | 高さの調整がしやすい | 硬めの感触が苦手な人には合わない場合も |
5.2 マットレス
マットレスも、睡眠の質に大きく影響する重要なアイテムです。寝返りが打ちやすく、体圧分散性に優れたマットレスを選ぶことで、肩や腰への負担を軽減し、快適な睡眠を得ることができます。
5.2.1 体圧分散性に優れたマットレス
体圧分散性に優れたマットレスは、身体の凹凸に合わせてフィットし、肩や腰への負担を軽減してくれます。特に、横向きで寝る方は、肩への負担が大きいため、体圧分散性の高いマットレスを選ぶことが重要です。ポケットコイルマットレス、高反発マットレス、低反発マットレスなど、様々な種類があります。自分の体型や寝姿勢、好みに合わせて選びましょう。
5.3 その他グッズ
枕やマットレス以外にも、肩こり解消に役立つグッズはたくさんあります。
5.3.1 温熱シート
温熱シートは、肩の血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果が期待できます。寝る前に貼ったり、肩が凝っていると感じた時に使用したりするのがおすすめです。蒸しタオルで温めるのも効果的です。
5.3.2 ストレッチポール
ストレッチポールは、背中の筋肉をほぐし、姿勢を改善する効果があります。寝る前にストレッチポールを使って簡単なエクササイズを行うことで、肩こりの予防や改善に繋がります。肩甲骨を動かすことを意識したストレッチと組み合わせるとより効果的です。
5.3.3 マッサージボール
マッサージボールは、ピンポイントで凝り固まった筋肉をほぐすのに役立ちます。肩甲骨の間や首の付け根など、特に凝りやすい部分にボールを当てて、ゆっくりと圧をかけたり、転がしたりすることで、筋肉の緊張を緩和することができます。入浴中に使用すると、よりリラックス効果が高まります。
自分に合ったグッズを取り入れることで、肩こりの悩みを軽減し、快適な毎日を送りましょう。
6. まとめ
肩こりは、寝方と密接な関係があります。高すぎる枕や低すぎる枕、うつ伏せ寝、同じ側ばかりで寝るといった寝方は、肩こりの原因となることがわかりました。自分に合った高さの枕を選び、仰向けまたは横向きで寝るように心がけましょう。さらに、肩こりの原因は寝方以外にも、デスクワークや運動不足、冷え性、ストレス、猫背など、様々な要因が考えられます。これらの原因を理解し、日常生活で改善していくことが大切です。
肩こりの改善策として、鍼灸は血行促進、筋肉の緊張緩和、自律神経調整に効果が期待できます。また、寝る前や朝に行うストレッチも効果的です。肩甲骨はがしや首回し、腕回し、肩甲骨寄せなど、簡単なストレッチを習慣に取り入れてみましょう。さらに、体圧分散性に優れたマットレスや温熱シートなどのグッズも、肩こりの改善に役立ちます。自分に合った方法で、肩こりのない快適な毎日を送るために、この記事を参考に、今日からできることから始めてみてください。
何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。
あなたへのオススメ記事
- 健康について,治療について肩こり高血圧は危険信号?原因と鍼灸による対処法を徹底解説!
- 健康について,日常について秋バテ防止!
- 健康について肩こり解消に筋トレは効果あり?鍼灸との併用で最強の肩こり対策!
診療時間
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 15:00~19:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
■ 休診日 日曜・祝日・水曜午後・土曜午後

〒537-0002
大阪府大阪市東成区深江南1丁目13−4
シャトーブラン BI HORIE 1F
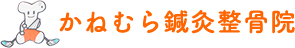
 お問い合わせ
お問い合わせ





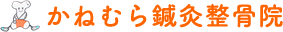
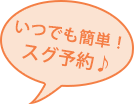
 LINEでお問い合わせ
LINEでお問い合わせ

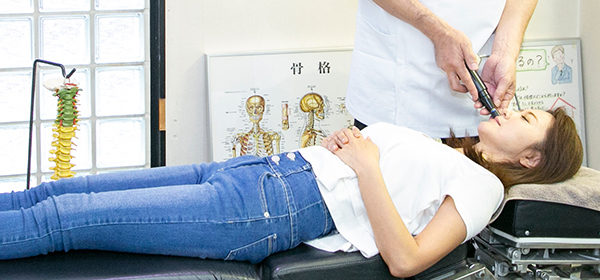


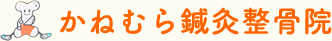
 ご予約・お問い合わせはこちら
ご予約・お問い合わせはこちら